キャリア入社社員対談
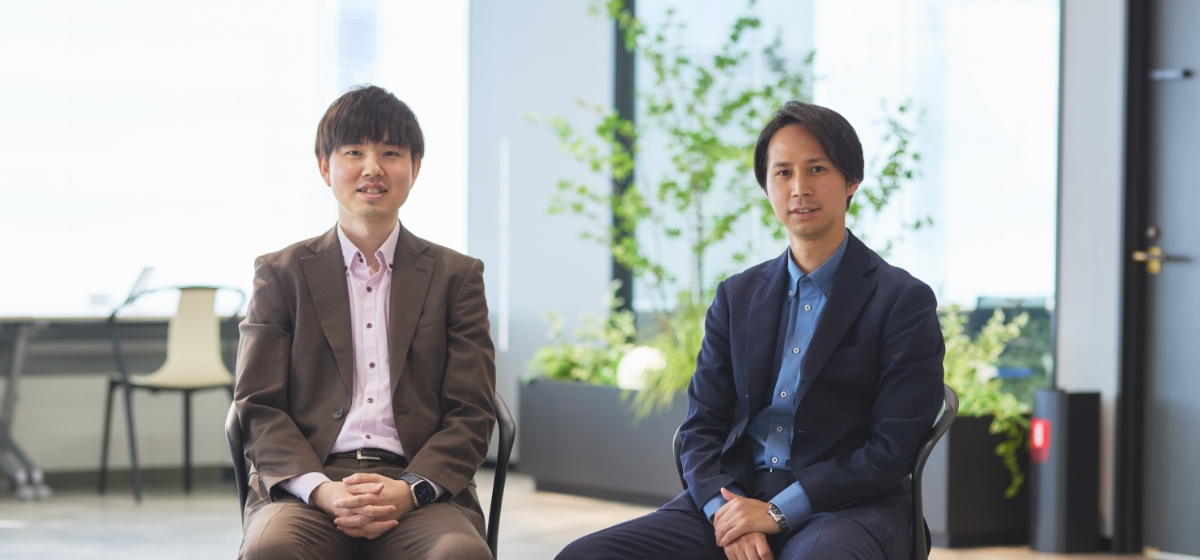
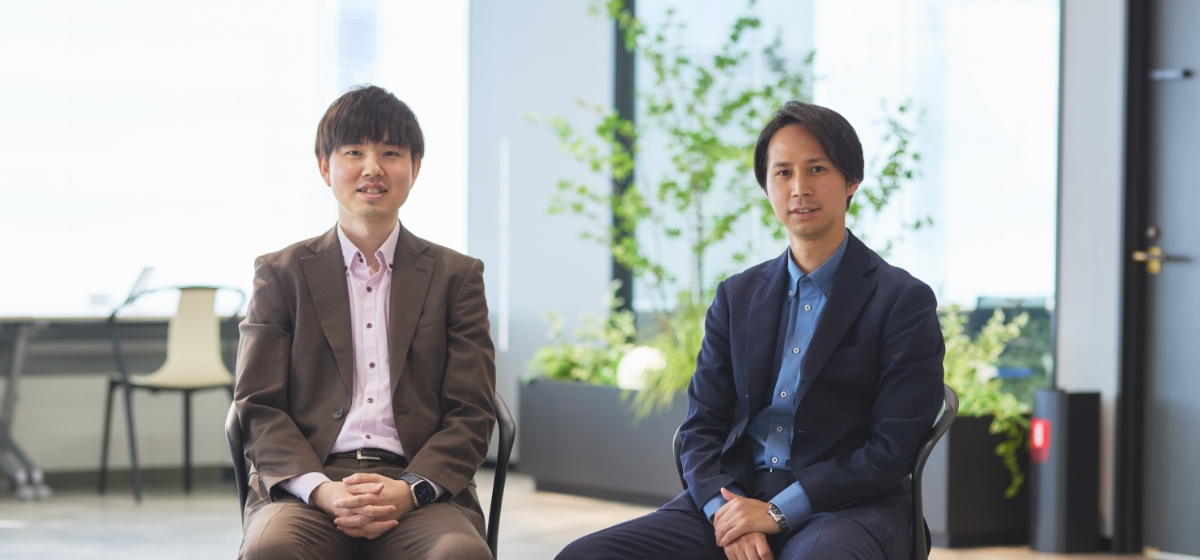
インタビュー動画はこちら!
 D.N
D.N
私の前職は金融機関で、30歳を前にこのままジェネラリストとしてキャリアを重ねていくのではなく、スペシャリスト的な働き方をしたいと考えるようになりました。言葉を換えれば「手に職をつけたい」。三菱UFJ信託銀行に関心を抱いたのは、「社会・お客さまの課題を解決できるプロフェッショナル集団」を掲げており、それが私の目指したい姿と一致したからです。なかでも、証券代行業務は年々注目度が高まっていた領域で、当時は「物言う株主」が話題にもなっていました。デットファイナンス以外の方法で企業の成長を支えたいと考えていた私は、ぜひチャレンジしてみたいと転職を決意しました。
 K.T
K.T
私が転職したのは、監査法人系のコンサルティングファームでM&A業務に従事していた際、歴史のある上場企業がやむなく祖業を手放す事業売却に携わったことがきっかけです。事業を切り出すことは、その従業員も切り出すことを意味し、非常に厳しい決断となります。コーポレートガバナンスの高度化や企業価値向上のための資本効率の改善など、M&Aに至る前にできることがあったのではないか。企業価値を高めていれば祖業を手放すことにはならなかったのではないか。そんな想いから、日本企業のポテンシャルを顕在化し、企業価値向上をご支援できるような業務に携わりたいと思いました。
 D.N
D.N
それぞれきっかけは違いますが、企業の持続的な成長を実現し、企業価値向上を支援するスペシャリストを目指すという点で志を同じにしていますね。
 K.T
K.T
それは間違いありません。

 D.N
D.N
一般に、証券代行機関は「株主名簿管理人」とも言われ、上場企業から委託された株主名簿作成や議決権、配当金に関わる事務を行なうだけと思われがちです。しかし、実際には年に1回の株主総会の運営支援を行なうだけでなく、年間を通したSR/IR(Shareholder Relations/Investor Relations)の支援や企業のガバナンス高度化に向けたコンサルティング、さらにはサステナビリティ対応まで総合的なソリューションを提供することで企業価値向上に向けた活動を行っています。
 K.T
K.T
とりわけコーポレートガバナンス・コードの改訂や、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた、いわゆる東証要請によって企業の意識、投資家の意識にも大きな変化が生まれました。それに伴い最高の意思決定機関である株主総会にも大きな変化が起きています。
 D.N
D.N
株主提案や議決権行使に積極的な姿勢を見せる投資家も増えました。しかし、株主提案が必ずしも顧客企業の経営方針と合致するわけではありませんから、その対策として普段からのエンゲージメントも重要になっている。そのため私たちも株主総会を運営する総務部・法務部だけでなく、経営企画部やIR部門、人事部など多くの部署と関わります。いかにしてガバナンスを向上させ、企業価値を上げていくかは全社的な問題ですからね。
 K.T
K.T
株主総会の在り方が変わり、これまで以上に信任投票の場になりました。私がM&A業務で経験した祖業を手放した企業も、株主総会で選任されたボードメンバーによってその方向性が決まりました。それほど株主総会の役割は重要なものになっています。

 D.N
D.N
私たち証券代行営業部門はスペシャリストであり、ジェネラリストでもあると思います。株主総会に関しては総会運営に関するコンサルティングから各種勉強会の開催、リハーサル支援、当日の運営や集計まですべてをこなすスペシャリストです。しかし、企業価値向上を実現するアプローチは多岐にわたり、チームとして多面的に企業を支援していかなければなりません。フロントとして企業と接するのは私たちですが、その後ろには各専門領域の多くのスペシャリストが存在しています。そのスペシャリストを各企業様のニーズに応じてチームアップしていくのも、フロントである我々の重要業務になっています。
 K.T
K.T
凄まじい数のスペシャリスト、プロフェッショナルがいますよね。ESG格付を専門とする人財やコーポレートガバナンスの専門家。機関投資家とのエンゲージメントや個人投資家対応の専門家など、多くの「知見」と「経験」が私たちを支えてくれています。株主総会に向けた準備を進めていく中で、色々な課題やニーズ、企業価値向上に向けたヒントが生まれるわけですが、そこで専門家たちの知見を最大限活用できるところが三菱UFJ信託銀行の大きな強みです。
 D.N
D.N
一方で、私たちもプロフェッショナル集団の一員だからこそ、不断の自己研鑽が求められます。上場企業は社会の公器でもありますから、その経営陣と対等に議論を交わし、提案するためには広く、深い知識と確かな見識が必要です。
 K.T
K.T
社会情勢や株主・投資家の動向とニーズをキャッチアップするために、社内では頻繁に勉強会が開催されています。二・三日に一回は何らかの勉強会が開かれているのではないでしょうか。勿論、すべてに参加するのではなく、必要に応じて個人でピックアップします。もし当日参加できない場合においても勉強会の様子は録画され、WEB上で確認できるようになっています。
 D.N
D.N
書籍などで自主的に学ぶことも多いですね。金融機関のオフィスは整然としたイメージがありますが、我々の部署は書籍スペースが常設されており、山のように専門書が積み上げられています。こうした専門性を深めるための制度や企業風土が根付いていることも三菱UFJ信託銀行の大きな特色でしょう。

 K.T
K.T
もう1点、三菱UFJ信託銀行の特色として「若手でもキャリア入社社員でもチャレンジできる風土」があると思います。勿論プロフェッショナル集団としてミスは許されませんので、任せきりではありません。周囲には実力者が脇を固めてしっかりサポートします。
 D.N
D.N
そうしたチャレンジできる風土の中で、キャリア社員に強く求められているのは何だと思いますか?
 K.T
K.T
「異なる着眼点」と「異なる専門性」でしょうか。証券代行業務は、会社法や過去の判例などを裏付けとした昔ながらの株式実務が中心でありながら、近年ではバーチャル株主総会や電子提供制度などのデジタルを活用した新たな実務も登場しています。これらは一例に過ぎないですが、実務が変化していく中、これまでの固定観念にとらわれずに新たな目線・着眼点でベストプラクティスを形成していくことが期待されていると思います。またキャリア入社社員ならではの異なる専門性も求められていると思います。例えば、私であればファイナンスの知識等、社内に伝播し、既存の知見と掛け合わせていくことが組織力向上につながると考えています。
 D.N
D.N
私は銀行でデットファイナンスしか経験していないので、前職での知識を現在の業務に直接的に活用しているわけではありません。しかし基本的なビジネスマナーや、論理的思考能力、コミュニケーション能力、ストレス耐性といった社会人としての強度は伝えていきたい。また業務キャッチアップの早さや収益化のスピード、業務フローに対する意見提言も他社を知っているキャリア入社社員だからこそ会社に提供できる価値だと思います。
 K.T
K.T
近年はキャリア入社者も増加し、多様なバックグラウンドを持つメンバーが活躍しています。その分、お客さまの多様なニーズへの即応力も高まっています。キャリア入社社員の知見や経験がさらに三菱UFJ信託銀行の強みである専門性の深化につながればいいですね。
